
現役予備校で既卒(浪人)部門設立の経験もある予備校講師経験者が、多くの浪人生の「怖すぎる失敗談」を紹介します! 浪人するか迷っている方、失敗したくない方は必見です。
・
浪人失敗談1「1年間普通に勉強したのに、伸びなかった!」


浪人して「1年間普通に勉強したのに、伸びなかった!」という人も少なくありません。1年間勉強して、なぜ志望校に落ちることがあるのでしょうか?
はい。まず、誤解があるのですが、浪人生活は実は1年間ありません。予備校が4月上旬にスタートなら、共通テストまで約9か月です。失敗した方の中には、まだ1年もあるとイメージして、スタートダッシュに失敗した例が多く見られます。
浪人のスタートは、正しくは、合格発表の日です。国立組は、後期は簡単には合格できないものと考えて、後期発表前にスタートを切ってください。
また、一応勉強は続けたが、1日の勉強時間が短かったという失敗例も多いです。
大手予備校の調査によると、早慶に合格した浪人生の平均の勉強時間は1200時間でした(授業除く)。期間を9か月と考えると、1ヶ月あたり130時間、1日4時間半が平均です。例えば、予備校の授業が1日6時間(90分の場合は4コマ)あるとすると、授業を含めれば、約10時間半の勉強時間となります。
また勉強時間が少なすぎた方の中には、予備校の授業を受ければなんとかなるでしょ?という誤解があった方も目立ちます。
高校受験塾が、過保護すぎることにも背景にあります。高校受験は、塾側が授業や宿題を通じて、塾に来るだけである程度得点できるシステムを作り上げている面があります。しかし、大学受験は量や質ともに高校受験と比較にならず、授業と宿題でカバーできる範囲はわずかです。
筆者の予備校講師時代、午前中の授業だけを取っていたある浪人生がいました。残って自習してゆくよう、何度も話しましたが、目を離したすきに帰宅していました。自宅で勉強がはかどるのは、よほどの勉強好きだけです(全体の5%未満)。結局志望校には遠く及ばず、浪人生活を終えることになってしまいました。
このほか、現役時代からの勉強法が誤っているケースもよく見られます。
浪人失敗例2 夜型生活になり伸びなかった!
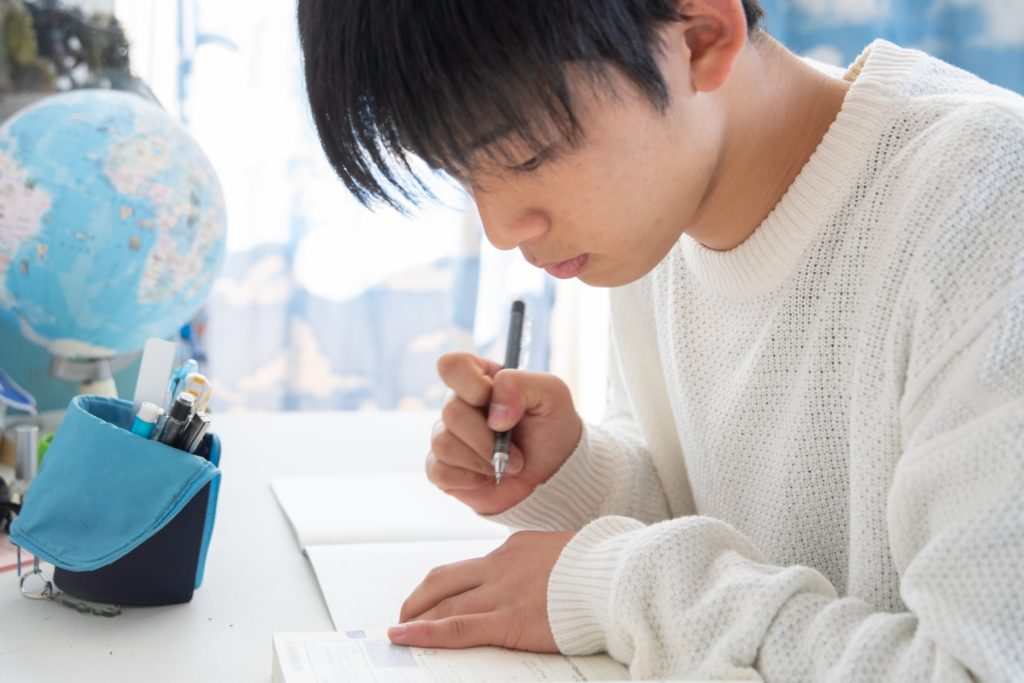

夜型生活になり伸びなかったとは、どういうこと?
はい。高校生の間は8時半ごろに、高校へ行くことが当たり前の課題でした。しかし、浪人生は、毎日授業がある「本科生」以外は、自己管理になります。本科生も、自由度が高い、入校前の春休みや、入校後の夏休みが、1つのヤマ場になります。
人間には体内時計が備わっており、睡眠を含む1日のサイクルが、自動的にコントロールされています。しかし、地球の1日の長さは遠い昔も今も同じというわけではなく、人類の体内時計は1日25時間程度に設定されていると言われます。
夜型は、誰にでも自然に起きてしまう!
そのため何もしなければ、夜23時に寝た人は、翌日0時ごろにしか眠くならない流れが、自然に起きてしまいます。これを放置すると、徐々に寝る時間が遅くなり、明け方にしか眠れなくなります。すると、毎日、午前中の体調が整わなくなることで、ほぼ100%浪人生活に失敗します。
実際の失敗例
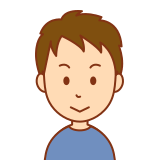
浪人し、週に3日程度予備校に通いましたが、夜型になってしまい、本調子が出たのは秋頃。1年をふり返ると、思ったほど勉強時間が取れず、志望校であるMARCHに届きませんでした。
夜型になるのを防ぐひとつの手段が、予備校の本科生になることや、午前中の単科の授業を取ることです。しかし現在は、予備校の本科生では家計が厳しい、という場合がよくあります。どのように、朝型をキープすればよいのでしょうか?
朝型キープの3つのコツ
① 夜22時ごろに勉強を打ち切ること
後がない浪人生は、不安から、つい深夜まで勉強をしてしまいます。しかし、夜間には体内時計が作動し、自然にリラックスモード(副交感神経優位)に入ります。夜遅く机に向かっていると、脳は、緊急事態が起きたと判断し、覚醒物質を出して作業を継続させようとします。
わかりやすくいえば、カフェイン入りのドリンク剤を飲みながら勉強をしているのに近い状況です。これは、本来の集中力とは異なり、実際の学力は伸びてこないことが多くなります。
どんなに絶好調だと感じても、必ず夜22時には勉強を打ち切って、23時の就寝を目指すことが、1つ目のコツになります。
② 朝の儀式を外さないこと
1日を25時間と認識している体内時計を、起床後にリセットすることが必要になります。例えば、カーテンを開けて太陽の光を浴びること、朝食を取る、シャワーを浴びるなどが効果的です。
③ 朝の行き場を作ること
予備校の本科生にならない場合、たとえば朝食を朝マックにして1時間程度の勉強をし、その後朝9時に図書館に入るなど、朝の行き場を作ることが非常に大切です。自宅学習の日であっても、午前中は1度外出したほうがペースをつかめます。
もし友人に同級生がいれば、マクドナルドや図書館などで待ち合わせをすることも有効です(ただし、目標が低い友人の場合は、遊んでしまい逆効果になります)。
▢ 夜22時ごろに勉強を打ち切っているか。
▢ 朝の光を浴びる、朝食、シャワーなど、朝の儀式があるか。
▢ 予備校の授業、または朝マック→図書館など、朝の行き場は決まっているか。
人気記事 浪人成功の本当のコツ|やること、理系・文系別、遊び、3月、旧帝大など、元予備校講師が完全伝授!
授業を5倍生かす SQ4R読書術を、高校での授業や、高校生の勉強法に生かす
勉強法を立て直す 【特別寄稿】偏差値45、50、55からの大学受験・一般選抜の勉強法|英語、数学、社会、古文、理科の勉強法裏ワザを完全公開!
浪人失敗例3 勝敗を分ける「英語」が伸びなかった!
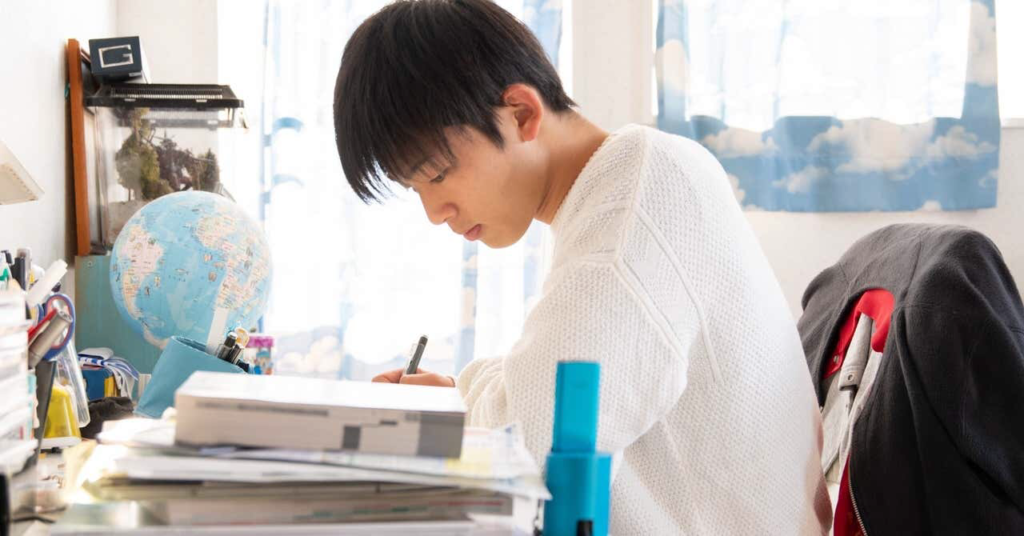

英語は配点が高いから重要と、よく言いますよね?
はい。それも正しいのですが、もう少し深い理由があります。それは、英語が唯一の「真の積み重ね科目」ということです。
地歴公民は、中学校でも習いますが、高校では初めからもう一度習います。例えば日本史なら、高校で改めて縄文時代から学び直します。理科も同様です。国語は中学のときに苦手科目であっても、高校から力を入れれば伸びてきます。
一方英語は、中3から高1で苦手だった場合、浪人してかなりの量勉強をしても、苦手が改善されにくい科目です。「真の積み重ね科目」である英語は、基礎が不十分な場合、スタート時の偏差値が50ならずっと50のまま、45ならずっと45のまま終わることが多い、鬼門とも言える、独特な科目です。
実際の失敗例
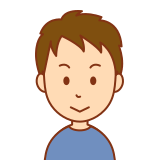
高校受験のリベンジで、大学受験でMARCHを目指し、英語漬けの日々。基本となるはずの文法の問題集を、何周も回したのに、偏差値はずっと50前後のまま。日東駒専にも届かず、非常に不本意な結果となってしまいました。
なぜ英語は入試で重視されるの?
大学受験において英語の配点が高いのは、なぜなのでしょうか?
今後の国際的なボーダーレスの社会に合わせて、という理由だけではありません。英語の点数が高いことが「中1から高3にかけて一度もサボらなかったことの証明になる」という要素もかなりあります。リカバーするポイントは、単語と文法事項、そして中文和訳(英文解釈)です。
具体的なやり方は、下のページにあります。
高校生の教科別勉強法を予備校講師に聞く
▢ 英語は偏差値50以下なら必ず伸び悩み、決定的な差を付けられる教科。
▢ 英語は、単語と文法事項、そして中文和訳(英文解釈)にカギがある。
浪人失敗例4 大学に進んだ同級生と遊んでしまった!


大学に進んだ同級生と、毎週遊んでいて、受験に失敗した先輩がいます。
はい。それも浪人生によくある失敗例です。同じ年齢とはいえ、一方が大学生になると、アルバイトや遊び、恋愛の話題など、価値観が大きく異なってきます。
合格するまでは遊びを断るのが一番ですが、全て誘いを断るのはやりづらいという場合には、「ランチだけ」がおすすめです。夜に会うと、だんだん盛り上がり、お互いにもう少しならいいやとなってしまいます。例えば、「土日のランチにしか遊べない人」とのイメージを作ってしまうのが、おすすめです。
▢ 大学生とは極力会わない。例えば、「土日のランチにしか遊べない人」とのイメージを作る。
人気記事 浪人成功の本当のコツ|やること、理系・文系別、遊び、3月、旧帝大など、元予備校講師が完全伝授!
授業を5倍生かす SQ4R読書術を、高校での授業や、高校生の勉強法に生かす
勉強法を立て直す 【特別寄稿】偏差値45、50、55からの大学受験・一般選抜の勉強法|英語、数学、社会、古文、理科の勉強法裏ワザを完全公開!
浪人失敗例5 理科、数学の質問環境がなかった
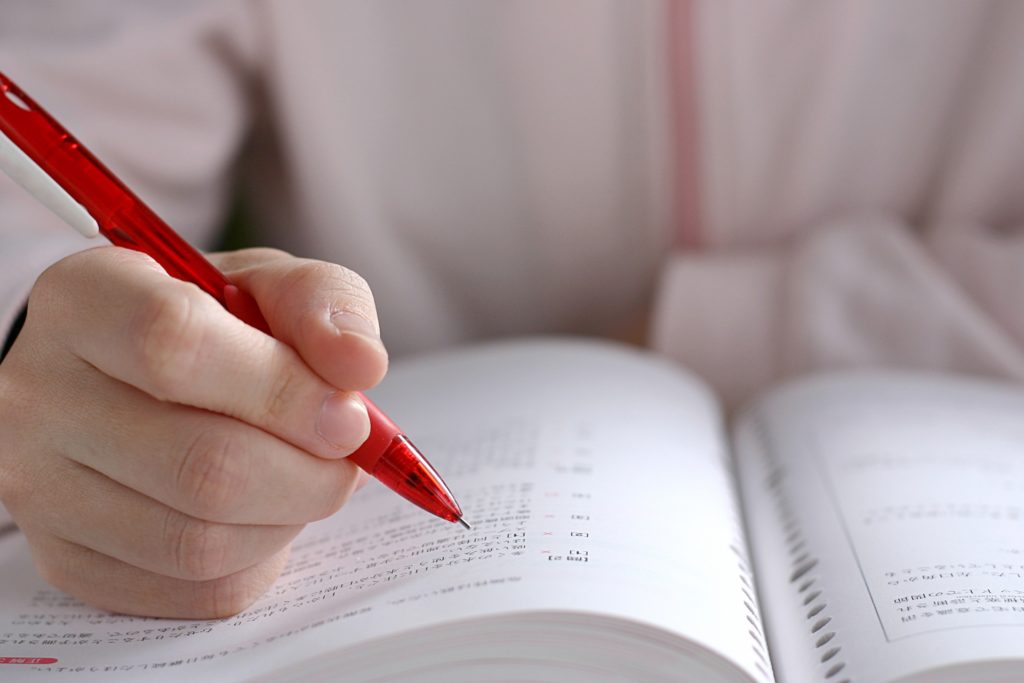

大学に進んだ同級生と、毎週遊んでいて、受験に失敗した先輩がいます。
理科、数学の質問環境がなかったとは、どういうことでしょうか?
調べれば何とかなることが多い英国社に対して、理科、数学を質問できる環境は必須です。質問をしないことで、正直腑に落ちない知識や解き方を、分かったことにしたり、無理に暗記したりしてしまうことが、得点力の向上を大きく妨げます。
できれば予備校講師、最低でも大学院生に、週数回程度は質問できる環境の確保が重要です。各予備校ごとの質問環境や、スマホで質問できる仕組みは、以下の記事に掲載してあります。
関連おすすめ予備校ランキング 元予備校講師が文系・理系別に予備校を徹底比較!
浪人失敗例6 文系数学、理系の国社で失敗
文系数学・文系理科
国立文系志望者は、数学の勉強時間は自然と短くなりがちではないでしょうか?
もともと数学が苦手、面白みを感じないので勉強時間が減る、週に1、2回しか触れないため伸びていかないというプロセスを歩みがちです。国語や社会でライバルの文系生に差をつけるのは難しいですが、数学なら不可能ではありません。毎日触れることが必要です。(理科にも同じことが言えます。)
実は、数学には効果が出やすい勉強法があり、文系生はその点で誤解があることが多いです。
勉強法【独自】元予備校講師が特別記事だけで明かす、受験成功術
理系国社
国立理系志望者は、国語や地歴公民の勉強時間は自然と短くなりがちではないでしょうか?
もともと国社は苦手、面白みを感じないので勉強時間が減る、週に1、2回しか触れないため伸びていかないというプロセスを歩みがちです。国語は共通テストであっても本格的な学力が必要です。古文をメインに、漢文、現代文は少なめの時間をかけて対策していきます。
また、倫理、政経、現代社会は暗記科目なので、秋以降に回すという国立理系志望の生徒も目立ちます。しかし、共通テストは、基礎軽視の付け焼刃の暗記では誤答する性質が高いため、1学期から基本を丁寧に学ぶことが重要です。
浪人失敗例7 早慶や旧帝大の壁を破れなかった!

勉強を重ねていけば、日東駒専の学力がMARCHに、MARCHの学力が早慶にランクアップしていくと考えている人がいます。しかし、MARCHと早慶の間には勉強量で乗り越えられない壁があることも事実です。
早慶、旧帝大などに合格する生徒には、以下のような特徴があります。
- 小中学校では、理解できない授業がほとんどなく自然体で上位にいた。
- 苦手科目はあっても、総じて勉強が好き。または特に苦にならない。
- 受験勉強を通じて新たな発見があり、興味がわくことがよくある。
- 教科のなかで、受験に直接役立つもの以外も、つい読み込んでしまう。
- 参考書の暗記事項を隠して覚える、チェックペンで覚えるといった受け身の勉強法をほとんど用いず、自分なりの勉強法を見につけている。
- 計算(理系)や活字を読むこと(文系)に、苦手意識はほとんどない。
- 何も考えずに過ごすことが苦手で、常に考えごとをしてしまう。
- 適度にざわざわした環境よりも、まったくの無音空間のほうが勉強がはかどる。
たしかに、早慶、旧帝大を狙う生徒が、MARCHや地方国立で止まるケースが多く、ひとつ上をめざしておくことは重要です。諦めろという訳ではなく、無謀な受験計画を立てないようにという意味です。
全ての受験生に、早慶や旧帝大に合格する「可能性」があることは否定しませんが、高校や予備校の、指導歴のある先生に相談してみることも大切です。
関連 浪人成功の本当のコツ|3月、まずやること、遊び、旧帝大・早慶、科目別など、元予備校講師が完全伝授!
浪人失敗例8 300時間勉強する前にギブアップする
資格やビジネスでは、最初の1000時間を越えると、見える世界が変わると言われています。
受験の教科に関しては、予備校講師の経験から言えば、まず300時間の集中勉強が、苦手脱出のめどになります。例えば、数学が苦手で浪人をしてしまったなら、3月に1日10時間数学の勉強に取り組んでみてください(ある程度単元を絞ること、また勉強法を改めること)。4月には数学の問題が「それほど苦でない」というレベルに必ず上がります。


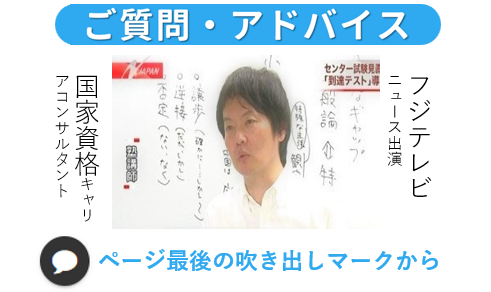
コメント